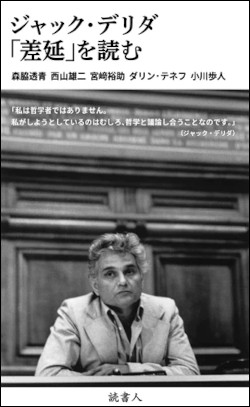ジャック・デリダ 「差延」を読む
[2023年4月/新書/224頁/]
著=森脇透青/西山雄二/宮﨑裕助/ダリン・テネフ/小川歩人
発行=読書人
目次:
はじめに
第I部 ジャック・デリダ「差延」解説
今日、デリダを読むために-入門書の時代
「差延」論文の紹介・差延の位置-なぜデリダのテクストは読みづらいのか
I 前置き-差延を語ることについて
差延とは何でないか-「説明する」とは何か
差延の戦略-目的地なき冒険
小括 (1)
II「差延」の語義分析-時間化と空間化
差延-「間隔化」と「時間かせぎ」
記号と差延-古典的記号概念
現代記号学の地平-ソシュール記号学
小括 (2)
III 差延のリソース
(1) ヘーゲル-「イェーナのヘーゲル」/差異、差異化、差延
コイレのヘーゲル論/「差異的関係」と「差異化する関係」と「差延」の差異
問いの形式と「意識」の特権-「とは何か」とは何か
(2) ニーチェ-『ニーチェと哲学』/諸力の闘争、差延としての「同じもの」
力
「同じもの」のポリティカル・エコノミー
解釈-「素朴さ」の擁護
(3) フロイト(バタイユ、レヴィナス)-痕跡と記憶/死の賭け/現前したことのない過去
精神分析と差延
『科学的心理学草稿』における記憶論-間隔化
保留、遅れ、事後性のモチーフ-時間かせぎ
一般経済と限定経済-バタイユ、死への賭け
無意識は潜在性ではない-事後性
現前したことのない過去と「帝国主義」-レヴィナス
小括(3)
IV 差延とハイデガー
「揺るがし」の思想
「存在のエポケー」と差延
(1) 差延と存在論的差異
「存在の真理」の道を通り抜ける
(2) 痕跡と形而上学のテクスト-痕跡の抹消の痕跡
(3) 形而上学の外部と「差延」という名称-存在の「手中」からこぼれ落ちるもの
「本来的」な翻訳?
ノスタルジーを超えた肯定/ロゴス中心主義
小括 (4)
総括・解説の終わりに
参考文献(日本語訳文献のみ)
第II部 討 論
研究活動の総括としての「差延」講演
否定神学の神だなんてとんでもありません……
人間の消失
人間の死
マラルメが実践する断絶を参照
差延の思想を練り上げるために
新しい哲学の登場
差延と弁証法との親近な関係
両義的なテクスト
沈黙が雄弁に物語る
「差延」の前提にある「差異」
神秘主義の罠を斥けるために/中動態を喚起しながらも……
否定神学に見えてしまうテクスト
不親切、大雑把、中途半端、乱暴……
初期デリダの可能性が集約された論文
「差延」以後への示唆
保留され、発展することのかかった問題
哲学者として認めてほしかったデリダ
戦略的につくられたテクスト
あえて形而上学的な言葉で……
デリダの議論は何を構造化しているか
力動的にみずからを構成しつつ、分割する間隔
五つのアスペクトで考える
「差延」のエコノミックな関係
率直さと、留保をかける慎重さの緊張関係
翻訳者の課題
デリダの入門書は何を読めばいいか
哲学的エリートの中で
二項対立の脱構築
デリダのドゥルーズへの評価
「事後性」について
サイバネティクスの問題系
言語学モデルをいかに拡張するのか
到来するもの
ハイデガーから引き継ぐ問題
誤配
散種
歴史からこぼれ落ちる残余
ノスタルジー
デリダがニーチェに見出したもの
過去にこだわりつづけ、未来の出来事を呼び込む
結局デリダは何がしたかったのか
後期デリダがコミットした問題
哲学的共同体は存在しうるか
アンガージュマン
「戦略」と「交渉」
マルクス主義的革命論との距離