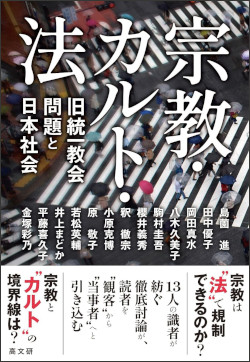宗教・カルト・法 旧統一教会問題と日本社会
[2024年10月/四六判/264頁/]
著=島薗 進/田中 優子/岡田真水/八木久美子/
駒村圭吾/櫻井義秀/釈 徹宗/小原克博/原 敬子/
若松 英輔/井上まどか/平藤喜久子/金塚彩乃/
発行=高文研
目次:
はじめに-問われる宗教と“カルト”の境界 | 鎌倉英也
第I章 宗教と家庭・性(ジェンダー)・子ども
●旧統一教会が力点を置く「家庭」
●浮かび上がる女性への蔑視
●宗教は女性を抑圧するのか
●「宗教二世」子どもへの強制を問う
●イスラム教における女性の位置
●「ジェンダー・フリー」を妨げるもの
●平等性の確保のために
〈column〉
岡田真水の軌跡と宗教 | 岡田行弘
個人と共同体のメカニズムについて考える | 釈 徹宗
宗教(わたしたち)と教団(あなたたち) | 原 敬子
イスラムは性役割をどう論じるか | 八木久美子
第II章 「信教の自由」と法規制
●旧統一教会問題から考える法と政治
●宗教問題に法は有効なのか
-「宗教法人法」と「法人寄附不当勧誘防止法」
はじめて行使された「質問権」
「配慮義務」で問われたマインド・コントロール
ピンポイントすぎる「法人寄附不当勧誘防止法」
あいまいな「認証」と「解散命令請求」
●日本国憲法が意図する「信教の自由」と「政教分離」
●日本社会のコミュニティが陥った機能不全
●「霊感」「霊性」「スピリチュアリティ」をどう捉えるか
●フランス「セクト規制法」と日本のあり方
弱者を守る「セクト規制法」の思想
「個人」の尊重と「中間団体」の役割
アメリカ的「宗教的マイノリティ」保護が移入された敗戦後の日本
宗教を「権威」のために利用してきた日本の歴史
「自己責任」「自助」の対極にある思想
●なぜ「信教の自由」と「政教分離」は結びつくのか
国家神道・家父長制との決別を謳った日本国憲法
「宗教団体」と「政党」の癒着を生み出す共通性
●「個人」の側に取り戻すべき宗教と社会
●法規制の前に必要な「社会的領域」からの批判
〈column〉
フランス「セクト規制法」2024年の改正問題 | 金塚彩乃
「信教の自由」と「良心の自由」 | 小原克博
「解散命令請求」の憲法論 | 駒村圭吾
分かり合えないもの同士で対話は可能か? | 櫻井義秀
祈りと宗教の乖離 | 田中優子
第III章 「宗教リテラシー」を高めるために
●「宗教リテラシー」とは何か
●問われる宗教教育の現場
●ロシアでは宗教をどう教えているのか
●欧米諸国の宗教教育事情
「わからない」ことを尊重する
●日本における「宗教リテラシー」の歴史
●「陰謀論」とIT時代の「宗教リテラシー」
〈column〉
「人権教育」と「宗教文化教育」のあいだ | 井上まどか
ポップカルチャー×神話×宗教リテラシー | 平藤喜久子
宗教の本義を考える | 若松英輔
むすびにかえて-宗教集団による人権侵害と「信教の自由」 | 島薗 進